意外と知られていない「喉仏(のどぼとけ)」について 豆知識をご紹介します
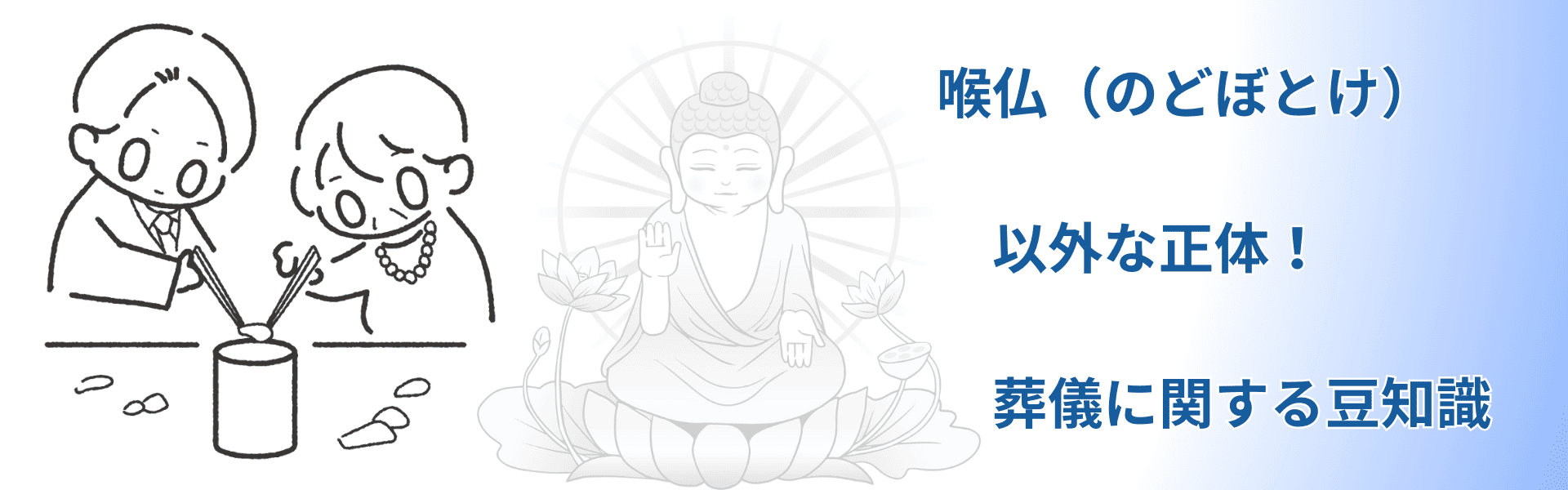
今回は、意外と知られていない「喉仏(のどぼとけ)」について、豆知識をご紹介します。
喉仏って何?正体と大切な役割
喉仏は、首の中央あたり、触ると少し出っ張っている部分のこと。医学的には「喉頭隆起(こうとうりゅうき)」と呼ばれています。その正体は、喉頭を覆っている**甲状軟骨(こうじょうなんこつ)**という軟骨の突起なんです。
この喉仏、ただの飾りではありません。私たちの体にとって、とっても大切な役割を担っています。

なぜ男性の方が目立つ?性別の違い
喉仏といえば、男性の方が女性よりも大きく目立つイメージがありますよね。これには、男性ホルモンであるテストステロンが大きく関わっています。思春期になると、テストステロンの分泌が活発になり、甲状軟骨の発達が促進されるため、男性の喉仏は大きく隆起するのです。
一方、女性にも喉仏はちゃんと存在します。しかし、男性ほどテストステロンの影響を受けないため、甲状軟骨の成長は緩やかで、喉仏が目立ちにくいのです。また、男性は声帯が長く太くなるため声が低くなるのに対し、女性は声帯の成長が男性ほど大きくないため、声の高さも男性より高い傾向があります。
成長の証!喉仏の変化と声変わり
思春期は、体にとって大きな変化の時期。男性の場合、喉仏が目立ち始めるのと同時に、声変わりも経験します。これは、発達した喉仏に合わせて声帯が長くなることが原因です。最初は不安定だった声も、成長とともに落ち着き、低い男性らしい声へと変化していきます。女性も思春期に声帯は成長しますが、喉仏が目立つほどの変化は見られにくいでしょう。
ちょっと気になる?喉仏が目立つ理由
男性であることはもちろん、体型によっても喉仏の見え方は変わってきます。首が細く長い方は、相対的に喉仏が目立ちやすい傾向があります。また、思春期の一時的な変化として目立つこともあります。
しかし、まれに甲状腺の病気などによって喉仏周辺が腫れて、目立つように見えるケースも。もし、急に喉仏が大きく腫れたり、痛みを感じたりする場合には、自己判断せずに早めに医療機関を受診してください。
仏教的な意味の喉仏とは - 故人の生きた証-
ご葬儀後の火葬の際、故人様の首の骨の一部が、まるで座禅を組んだ仏様の姿のように見えることがあります。この骨を「喉仏(のどぼとけ)」と呼び、ご遺族にとって、故人の面影を偲ぶ上で非常に大切な存在とされています。
医学的な喉仏(喉頭隆起)とは異なる、この仏教的な意味合いを持つ「喉仏」は、主に第二頚椎の軸椎(じくつい)という骨の一部であると言われています。この軸椎にある突起が、独特の形状を作り出すと考えられています。
喉仏を別の容器に
お身体全体のお骨とに収骨される方もいらっしゃれば、手元供養として小さな容器に納め、身近に置いて故人を偲ぶ方もいらっしゃいます。
喉仏を別の収骨容器にしたいという方は予めお伝えください。ご収骨の際に別の小さな容器をご用意してたうえで、火葬場へお伝えさせて頂きます。
ご葬儀は、故人との別れを告げる場であると同時に、残されたご遺族が新たな一歩を踏み出すための大切な儀式でもあります。家族葬の心幸(しんこう)は、故人の尊厳を守り、ご遺族の悲しみに寄り添いながら、未来へと繋がる温かいご葬儀を心を込めてお手伝いさせていただきます。

お見積もり・葬儀の資料をお送りします





