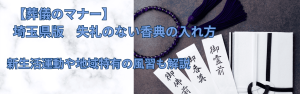【葬儀のマナー】「大往生でしたね」の一言に潜む注意点:ご遺族の心に寄り添う言葉選び
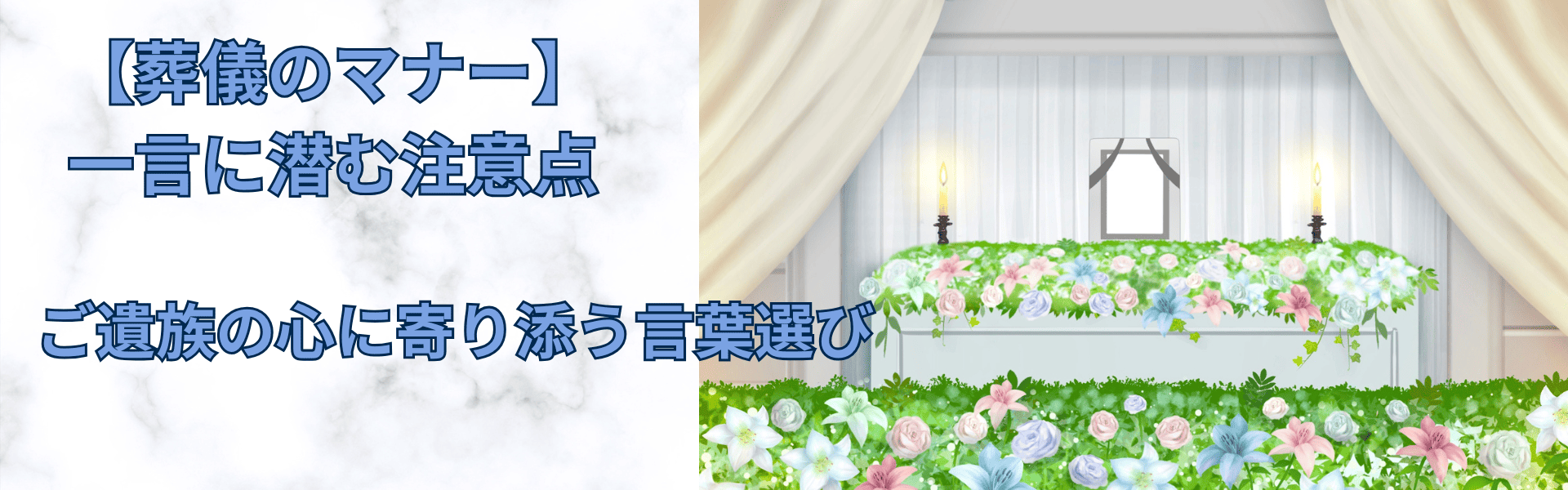
葬儀の場で、故人のご冥福を祈り、ご遺族を慰めるために言葉をかける際、私たちは様々な表現を用いることがあります。その中で、時折耳にするのが「大往生でしたね」という言葉です。一見すると、穏やかな最期を迎えた故人を偲ぶ、心温まる言葉のように感じられるかもしれません。しかし、この言葉を使う際には、細心の注意が必要であることを覚えておきましょう。
「大往生」という言葉の持つ意味合い
「大往生」とは、一般的に、苦しむことなく、天寿を全うして亡くなることを指す言葉です。高齢で亡くなられた方や、病床で長く苦しまずに旅立たれた方に対して、その人生を全うされたことを称える意味合いで用いられることがあります。
なぜ「大往生」という言葉に注意が必要なのか
この言葉が持つ意味合いとは裏腹に、ご遺族の心情によっては、必ずしも適切とは言えない場合があります。その理由は、以下の点が挙げられます。
- 悲しみの深さは人それぞれ: 傍から見て穏やかな最期だったとしても、最愛の方を失ったご家族の悲しみは計り知れません。「大往生」という言葉が、その深い悲しみを軽んじているように聞こえてしまう可能性があります。
- 複雑な感情を抱えている可能性: ご遺族の中には、「もっと一緒にいたかった」「何かできたのではないか」といった後悔の気持ちを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。そのような状況で「大往生」という言葉は、ご遺族の複雑な感情に寄り添えない、突き放したような印象を与えてしまうことがあります。
- 安易な言葉に聞こえる: 深い悲しみの中にいるご遺族にとって、「大往生」という言葉が紋切り型の、安易な慰めの言葉のように聞こえてしまうこともあります。
ご遺族の心に寄り添う言葉選び
では、どのような言葉を選べば、よりご遺族の心に寄り添い、弔意を適切に伝えることができるのでしょうか。
- まずは弔意を示す:
- 「心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「この度は、誠にご愁傷様でございます。」
- 「〇〇様のご冥福を心からお祈りいたします。」
- 「心よりお悔やみ申し上げます。」
- 「この度は、誠にご愁傷様でございます。」
- 「〇〇様のご冥福を心からお祈りいたします。」
- 故人のご様子に触れる場合:
- 「安らかにお眠りのこととお察しいたします。」
- 「穏やかなお顔を拝見して、少し安堵いたしました。」
- 「安らかにお眠りのこととお察しいたします。」
- 「穏やかなお顔を拝見して、少し安堵いたしました。」
- ご遺族の気持ちを気遣う言葉:
- 「今は、ゆっくりとお体を休めてください。」
- 「何か私にできることがございましたら、遠慮なくお申し付けください。」
- 無理に言葉を探すのではなく、静かに寄り添うことも大切です。
- 「今は、ゆっくりとお体を休めてください。」
- 「何か私にできることがございましたら、遠慮なくお申し付けください。」
- 無理に言葉を探すのではなく、静かに寄り添うことも大切です。
- 故人との思い出を語る(もし親しい間柄であれば):
- 「〇〇様には、いつも優しくしていただきました。あの笑顔は忘れません。」
- 「〇〇様との〇〇(具体的なエピソード)が、私にとって大切な思い出です。」
- 「〇〇様には、いつも優しくしていただきました。あの笑顔は忘れません。」
- 「〇〇様との〇〇(具体的なエピソード)が、私にとって大切な思い出です。」
まとめ
葬儀の場では、ご遺族の悲しみに寄り添い、慎重な言葉を選ぶことが何よりも大切です。「大往生」という言葉は、状況によってはご遺族の心を傷つけてしまう可能性も孕んでいます。表面的な言葉ではなく、心からの弔意と、ご遺族への深い配慮を持って、故人を偲び、ご遺族を慰めるように心がけましょう。
【公営】東松山斎場の家族葬・葬儀
24時間・365日専門スタッフが対応いたします。
電話:フリーダイヤル0120-001-727
【無料相談】【無料見積もり】